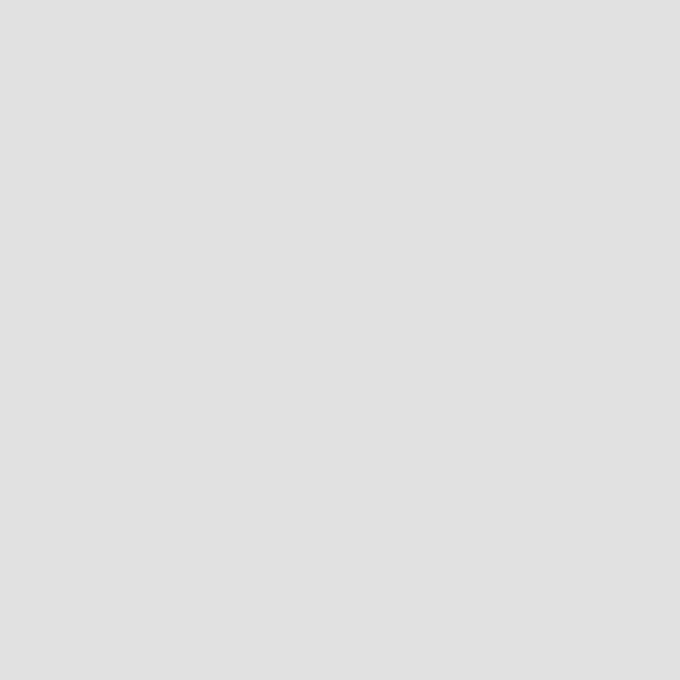偶然の出会いから、確信へ。はたらく場づくりへの想い。

石けんとの出会いは、偶然だった。訪れていた気仙沼の仮設住宅で、ワークショップを見学していた時だった。想像以上の参加者の熱気に、厨さんは驚いた。粉状の石けんにオリーブオイルを混ぜて、練って固め、好みのハーブや香り付けのオイルを加えるというプロセスを経て、世界で一つの石けんができあがるというもの。「他のワークショップに比べ参加している女性たちの熱心さを見た時に、これはいけるんじゃないかと、強く思いました」その時の光景が、頭の中から離れることは無かった。
震災直後の2011年の3月末には、東北支援を始めた厨さん。東京で翻訳会社を経営する傍らボランティアとして通い続け、7月には南三陸町への移住を決断。被災地の情報発信をしながら、日中はボランティアコーディネートに奔走し、夜は本業を続けるうちに、徐々に創業支援に携わるようになった。地元の漁師主催のバーベキュー小屋や、養蚕のまゆ細工の工房の立ち上げを手伝ったりするなど、復興に向けて新しい事業を提案して支える、ということを続けていた。そんな中、仮設住宅で見たあの光景が何度も蘇った。天然石けんを作ろうと持ちかけるも、誰も手を挙げない。「手作り石けんというと、匂いが強い廃油石けんのイメージが強すぎて、なかなか伝わらなかったんですよね。オリーブオイルを使うんだと説明しても、通じなかったんです」
可能性を感じていた理由の一つは、若い女性の雇用創出だった。現状は、高校を卒業したら大きな町へ出て、専門学校または大学へ進学し、卒業後はそのまま就職という道しか無い。地元で働きたい、仕事があったら地元に帰ってきたいという声が聞こえてくるものの、働き口がないため、まとまった休暇の時にしか帰省できないという現実があった。石けんづくりであれば、若い女性の仕事になるのではないか。そう感じた厨さんは、実現に向けて自ら動き出す。
三陸の沿岸部は、リアス式海岸。食べ物が豊富なことでも知られている。ではこの地域でハーブ石けんと作るとしたら、どうなるだろうと厨さんは考えた。「石けんの材料は食べ物だ、ということに気づいて。海からも山からも、豊富な材料が手に入る。地元ならではの豊かな石けんができるのではと」。近隣の素材を活かせば、石けん以外のスキンケアも出来るに違いない。新たな事業の可能性と確信を胸に、2014年の春に法人を立ち上げた。
信念と勢いで事業を立ち上げたものの、石けんづくりなどやったことも無かった厨さん。まずは教室に通い、ノウハウとスキルを身につけた。7割の建物を失った地域で、苦戦したのは工房の場所探しだった。選択肢が無い中で、築50年の山裾にある家を借りることに決めた。ただ、場所のわかりにくさ、不便なアプローチ、駐車場が無いなど、長期的に工房を構え続けることは考えにくかった。まずは、試験的に運用を、と2015年1月に「南三陸町石けん工房」をオープンした。

カラフルな経歴、ぶれない強さ。
実は翻訳会社を運営するほど英語が堪能な厨さん。ボランティアをしていた時も、国連などの国際団体の視察も受け入れたという。「学生時代にアメリカとカナダに留学、というより<遊学>でしたけど。ひたすら合気道をやっていました」と笑う。高校から続けている合気道は黒帯の腕前。英語は話せない、ならば、と留学前に二ヶ月取り組んだ猛特訓の成果はすぐに出た。日本人はおろか、アジア人が殆どいないようなアメリカの小さな町に本場のブラックベルトが現れたわけだ。一気に友達ができた。
卒業後は、一般企業に就職し、海外営業を担当した。二年働いた後、思うところがあり退職し、バックパッカーとして二年間世界中を放浪して回った。その後東京へ戻り、人事コンサルタントとして働き始める。ご実家が自営業だったこともあり、いつか自分で事業を立ち上げるための修行だと思い、全てを学びの場と考えた。人事コンサルタントのビジネスが順調に動き始めていたところ、リーマン・ショックで一気に事態は暗転。英語ができることを買われて、翻訳業に転職。「まぁ、これだけ色々経験すると、人間なんでもやって食っていけると思いましたね。失敗を恐れない。体当たりでいくようになりました」あっけらかんと笑う厨さん。ちょっとやそっとじゃぶれない芯の強さを見た。
いざ南三陸から、女川へ。
南三陸から女川へ来ることになったきっかけを聞いた。以前から交流のあった女川の仲間に、より長期的に使える工房を探しているという話をしていた時だった。そんな時、ちょうど今日空いた、という商店街の物件をその場で強く勧められたのだ。迷いが無かったわけではないが、厨さんは考えた。「たとえ失敗したとしても、店をやったほうが経験値は必ず溜まる。熱烈なバックアップを受けているのに、ここで考えさせてくださいは、男として無いな」と決断してからは早かった。話を聞いた翌日の2015年7月1日に、契約書にサイン。内装工事は最小限に留め、石けんのディスプレイと作業ができるスペースを設けた。家具を作ったり壁を塗るなど、自分たちでできる部分は手作りをし、工房をオープン。9月の秋刀魚収獲祭の日にプレオープンしてからは、突っ走ってきた、と話す。
南三陸石けん工房の最大の転機は、石けんの形とパッケージにある。作り始めた当初は、いわゆる石けんらしい大きさで、長方形で作っていた。特徴を出そうと考えた結果、形を正方形のキューブ型にし、パッケージを工夫した。「最初友人にギフトとして送ってみたら、あまりにも褒められるんですよ。お世辞じゃないことがわかってからは、いけると想いました」と厨さん。チョコレートのように箱におさまっている石けんは、高級感とかわいらしさを併せ持つ。


贈りたくなる、教えたくなる石けん。

2015年の春くらいから、工房を訪れた人に少しずつ売ることを始めた。当初は、お客さんのほとんどが、厨さんの知り合いだった。厨さん曰く、キャッチーな製品づくりをしていることが徐々に注目され、ラジオやテレビで取り上げられるように。メディアで知った工房の噂を聞きつけてきた人が訪れるようになった。
形をキューブにしてからというものの、写真を撮りたい、共有したいという人が後を立たない。そのかわいらしい姿はつい触りたくなるし、誰かにその存在を教えたくなってしまうのだ。SNSで写真をアップする人が増え、どんどん広まっていった。写真を見た人から、ウェディングの注文も入るようになった。そして、そのウェディングに参加した人が石けんの存在を知り、また注文が入る。こうして、口コミでファンの輪が広がっていく
現在は、注文に追いつかないほどの人気を見せている南三陸石けん工房の石けん。でも、厨さんはおごらない。「あくまでも手作りであることの価値があると思うんです。量産は考えていません」と厨さんは話す。材料にはこだわり、宮城で調達できるものだけを選ぶ。丁寧に一つずつ手作りをしていく、ぶれないものづくりの姿勢に共感する人が、ファンになっているのだ。
不定期に開催しているワークショップも、人気。数種類用意された色合いも効能も異なる素材の中から好きなものを選び、石けんを作っていく。何名かで作って、お互いにシェアする人が多いという。かわいらしい箱に入れて、持って帰ることができる。作ったばかりの石けんは、固形になるまで3日ほどかかり、その後アルカリ成分が中和するまで、一ヶ月ほど乾燥させてから使えるようになるのだそうだ。自分が作ったものが手元に届くのを待つ時間を楽しめるのも、魅力の一つだ。
南三陸石けん工房のこれから。
南三陸石けん工房の店頭には、笑顔がとても素敵な女性が立つ。彼女ならではのセンスがところどころに現れた店内で石けんを見ているだけでも、じわじわと豊かな気持ちになってくる。女性のお客様は、一つずつ選ぶことを楽しみ、男性のお客様は最初からセットになっているものを選び、買っていく。今後は、石けんが三つセットになった定番商品の他に、別のサイズの商品化も検討中。石巻の古民家カフェと組んで、新たな展開も考えているという。そしてなんと、台湾にある日本のアンテナショップでの販売も決まった。早くも、海外進出だ。
今年の10月には、駅前の物産センターへの出店を考えている南三陸石けん工房。新しいまちづくりの流れの中で、どんなふうに進化していくか注目したい。
女川こぼればなし。 厨さんが予想しなかった嬉しい流れが一つある。それは、女川の人たちが、女川のおみやげとして買っていくようになったことだ。新たな女川の顔として、町の人たちに愛されてはじめている石けん工房が、町と共に育っていく姿に心動かされる。
2016.03.10 Text : YUKA ANNEN Photo : KEISUKE HIRAI