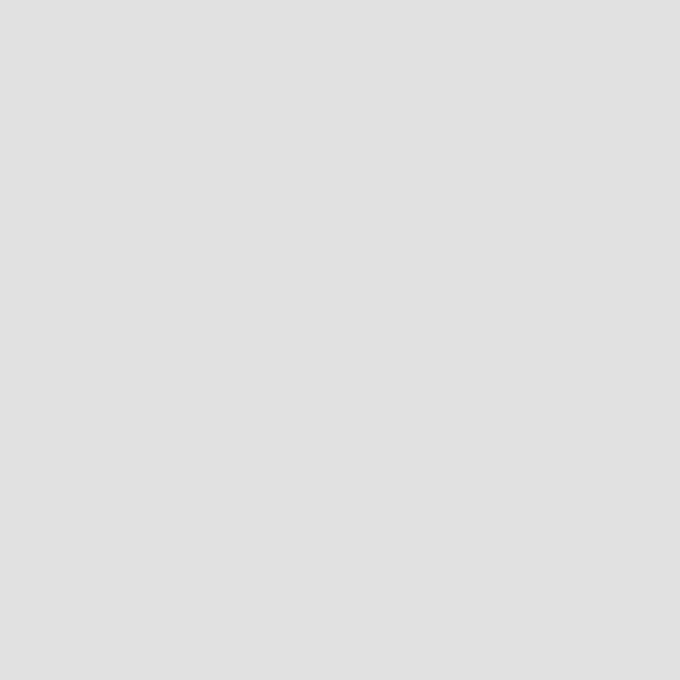女川が好きすぎて、離れられなかった。

震災後は、小さな子どもを抱えての再出発だった。便利さを追求したら、別の町へ移るという選択肢もあった。家族からは、子育てを優先するため、引っ越したいと言われていたという。「女川が好きすぎて、どうしても離れたくなかったんです」と宏太さん。家族を説得し、女川で暮らしていくことを決めた。一番魅力はやはり人だ、と話す。人間同士の距離感は近い。でも、役割や立場の線引きははっきりしている。
女川が震災後に復興を目指す中で、復興に向けた様々なプロジェクトに参加した。仕事に加え多忙を極めた結果、帰宅は毎日零時過ぎ。なんで女川のために、なんでそこまでやるのだと、家族にも言われたという。そんな宏太さんには、自分の生き様を通して伝えたいことがある。「田舎だから出来ないのではなく、場所はどこであろうが、やろうと思えばなんでもできる。それを子どもたちに伝えたいんです」と力強く話す。震災後に変わった自分を見てもらいたいのだ。
お金にはならないかもしれない。でもだからこそ、町の中や町外の人びととのかけがえのない出会いがある。それに気づき始めた自分がいた。仕事は仕事、プライベートはプライベートと分けていた宏太さんが、少しずつ変わっていった。人見知りでドライ、キャリアアップを狙っていく。以前は、そんな自分をかっこいいと思っていた。震災後の様々な体験を通じ、自分の小ささに気づいたという。宏太さんにとって、大きな転機だった。
同級生で始めた音楽イベント「我歴stock」。

お揃いのブルーつなぎがトレードマークの「女川福幸丸」。いまでは、町のイベントでは欠かせない存在だが、始めた当時は実績も無く、イベントプランニングなどやったこともない同級生の集まりだった。初期メンバーは5名。震災後の7月に、地元の居酒屋で初顔合わせをした。町を元気づけるために音楽イベントやろうという、のちに「船長」と呼ばれる代表の熱い呼びかけに、心を動かされたのだ。初代福幸丸船長には、女性を立てた。駆け引きもなく、気持ちだけでどんどん動いて行く真っ直ぐな同級生を応援しないわけにはいかなかった。
実のところはこうだ。一緒にやらないかと声をかけられた時に、面倒くさいことに巻き込まれたくないというのが本音だった。宏太さんの気持ちを動かしたのは、仲間のひたむきな姿だった。「友人は、お母さんを亡くしました。自分は、なにもしてあげることができない。でも、目の前に当人が前向きにがんばっているのに、自分は逃げ出そうとしている。一体自分はなにをやっているのか、と思い直したんです」参加すること決めてからの宏太さんの覚悟は、揺らぐことはなかった。
賛同してくれた地元の水産系の会社社長からの出資や応援してくれる町の人から集めた資金で、イベントを企画。2011年10月30日、震災からほんの半年強で「我歴stock」開催までこぎ着けた。有名な音楽イベントへのオマージュも込めたネーミング。あえて「がれき」という言葉を「我歴(我が歴史)」とし、イベント名に入れる決断をした。「いま考えると、ネーミングからして尖ってましたね。なにせまだ20代でしたから」そう言って宏太さんは笑う。その後は、「女川福幸丸」としての実績を作るために、町の人に頼まれたらなんでも引き受けた。プライベートが無くなるほど、空いている時間は注ぎ込んだ。家族からの非難もあった。でも、いまこそ女川のためにやらなければならない、という覚悟の元だった。
開催から5年目となった昨年の我歴stockは、多彩なラインナップのアーティストによるライブパフォーマンスや女川の女の子たちが参加したファッションショーから、伝統芸能の獅子舞まで、実に賑やかでカラフルな女川カラー全開のイベントとなった。新しい船長も就任。二代目も、女性だ。今では、次の世代にリーダーシップを譲り、若手の活躍を見守っている宏太さん。「福幸丸の活動で得た経験が、自分の仕事にも活かされています。実際にお金には代えがたいスキルが身につき、成長した実感があります。彼らにもそうなってもらえれば」と目を輝かせる。次世代を担う後輩たちに託す想いは熱い。

はじめましてから、はじまった。女川人生が変わった、復幸祭。
音楽イベントをやったことで実績ができた女川福幸丸。我歴stockに訪れた町の若手リーダーの目に止まった。2011年の終わり頃に、翌年の3月に向けた復興イベントの話が持ちあがり、そのメンバーに入らないかと宏太さんにも声がかかった。それまでは交流が全くなかった者同士が、はじめまして、と一人また一人と集まった面々。今では親しくしている町の重鎮の方々も、誰一人知らないような状態だった。町中で見かけたり、少し話したことがある程度で、戸惑いもあった。


集まったとは言え、やはりまだ震災から間もない時期。やるかやらないか迷っていた時に、やるべ、というリーダー格のメンバーの一言で、参加者の気持ちが一つにまとまったという。2011年の年末に話し合い、開催を決めた。それが、2012年3月18日に行われた「女川町商店街復幸祭〜希望の鐘を鳴らそう」。結果、1万人もの人が集い、町の伝説となった。のちにオープンした「きぼうのかね商店街」の名前も、この第一回目の復幸祭がきっかけとなった。
2012年以降、毎年開催されている復幸祭。年々規模も内容も進化している。今年は新しく出来た駅前エリアでの開催となる。委員会も例年通り発足し、準備に余念がない。そんな姿を見て、宏太さんは言う。女川は最強集団だ、と。「とにかく、スピード感がすごい。走りだすのも早い。問題が出ても、走りながら解決していく。」少人数で集中し、町全体を引っ張っていく。今は仲間と呼べる町の面々と急接近したきっかけをくれた、女川町復興祭。宏太さんや町の多くの人にとって、特別な存在だ。
将来の自分、これからの女川。

魚嫌いだった宏太さん。小学校以来の幼馴染の誘いで入社してからは、毎日魚を買って、毎日自分でおろした。自らの手で扱ったものを食べることによって、嫌い、が好き、に変わっていき、誇りを持って日々仕事に取り組めるようになった。時には全国各地に出向き、日々女川の新鮮な海産物を使った商品開発に取り組んでいる。そして、「将来的には、英語で海外と取り引きできるまでに成長したい」と意気込む。英語教育が女川で充実すれば、女川移住の魅力のひとつになるのではというのが宏太さんの意見だ。それが、女川を救うかもしれない、と。子どもから大人まで英語が話せる町、女川。そうなれば、インバウンドも怖くない。どこかエキゾチックな文化の空気が流れている町だけに、最初から世界に目を向けるというのも、女川らしい。
もう一つ、宏太さんには実現したい夢がある。二十歳という一番遊びたい時期に、遊ぶこと無く子育てに人生を捧げた奥様に、心から感謝しているという。実は、結婚式を挙げていない宏太さん。「口説ける水辺」と自ら銘打った海辺の観光交流エリアで、念願のウェディング実現、となるだろうか。お嫁さんのご両親に花嫁姿を見せてあげたいですね、そうはにかんだ。
女川こぼればなし。
2015年秋、ニューオリンズでの研修のため渡米。好奇心旺盛な宏太さんは、研修が終わっても町へ繰り出し、地元の人との交流を試みたという。本心はもっと話したかった、と宏太さん。密かに勉強している英語の成果を発揮したい気持ちでいっぱいに違いない。
2016.02.23 Text : YUKA ANNEN Photo : KEISUKE HIRAI